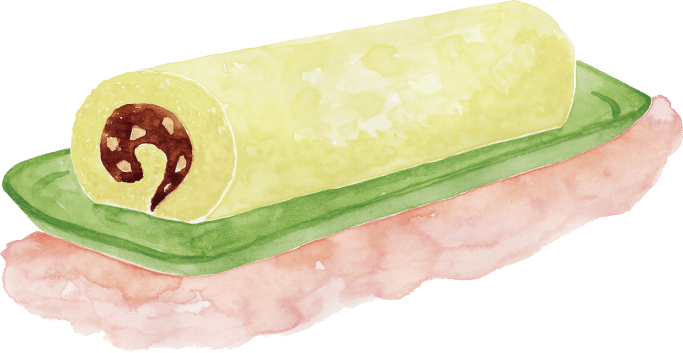ハタダ栗タルト
50周年記念小説
50th Anniversary Short story
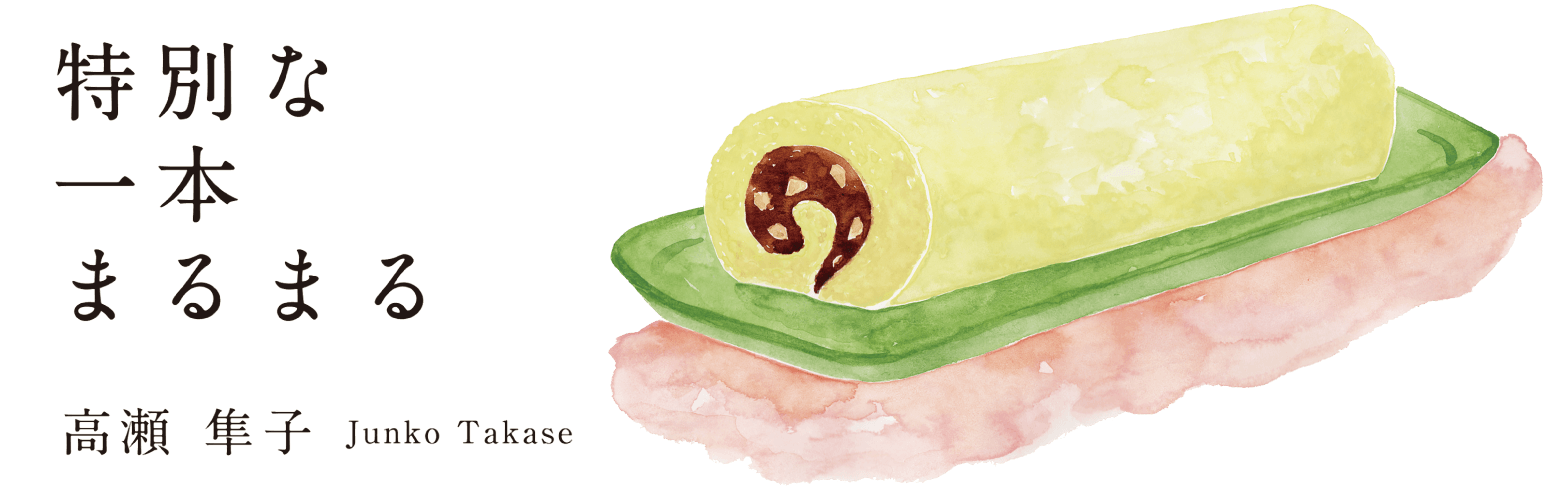
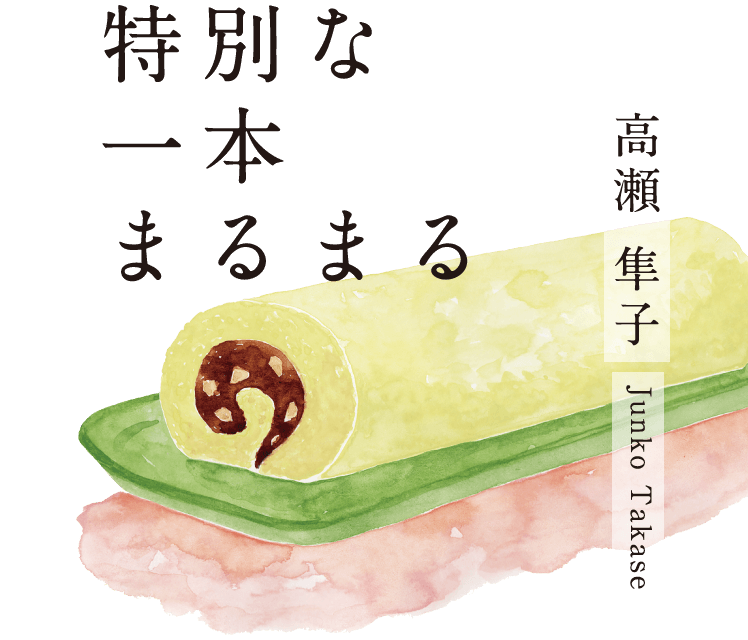
新居浜市出身の芥川賞作家 高瀬隼子さんに、
ハタダ栗タルトを題材にした記念小説を
書き下ろしていただきました。
※2025年11月26日 愛媛新聞掲載

©嶋田礼奈/講談社
高瀬 隼子(たかせ じゅんこ)
1988年愛媛県新居浜市生まれ。
愛媛県立新居浜西高等学校、立命館大学文学部卒業。
2019年「犬のかたちをしているもの 」 で第43回すばる文学賞を受賞しデビュー。2022年「おいしいごはんが食べられますように」で第167回芥川賞受賞。2024年『いい子のあくび』で第74回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。著書に『水たまりで息をする』、『うるさいこの音の全部』、『め生える』、『新しい恋愛』がある。
特別な一本まるまる
「気にしなくて大丈夫。失敗して覚えていくものなんだから」
先輩社員の慰めの言葉を思い出しながら、奈保は身を切り刻むように冷たい夜気の中を歩いていた。いっそ厳しく叱られた方が楽だったかもしれない。(ああすればよかった)(どうしてあそこで気付かなかったんだろう。なんか変だって感覚はあったのに)と、取引先とのやりとりを口頭だけで済ませた自分や、発注数の確認をおざなりにした自分を、頭の中に呼び出しては責め立てた。
一人暮らしのマンションまで電車で三駅の距離を、自分を罰するように歩き続ける。手袋を忘れてしまったせいで、指先がかじかむ。自分を許せず怒っているからこそ、なんとか泣かずにいられる気もした。乾いた頬に夜風が吹きつける。入社して八カ月。初めて一人で担当した案件での大きなミスだった。
一時間近く歩き続け、体というよりも、心がへとへとに消耗していたけれど、そのまま暗く狭い部屋へ帰る気持ちになれず、駅前のスーパーに吸い込まれるようにして入った。真昼のように隅々まで明るい店内で、奈保は息を吐いてようやく顔を上げた。
目に飛び込んで来たのは、〈ふるさとフェア~愛媛県~〉というカラフルなプレートだった。手書きらしい蜜柑の絵が添えてある。ふらふらと引き寄せられ、棚を見渡すと、見知ったお菓子や調味料、ジュースやお酒がずらりと並んでいた。ぐらりと足元が揺らぐような感覚がした。(東京におる、うん、地元じゃなくて東京におるよね)自問自答する声までも、自然と地元の言葉に還る。
一際、光って見えるものがあった。ハタダの栗タルトだった。個包装ではなく、一本まるまるの。すっと手に取る。ずっしりした重みを手のひらに感じた瞬間、奈保は生まれ育った新居浜でのことを思い出していた。
*
ハタダの栗タルトには苦い思い出がある。海ばあちゃんを傷つけたのだ。
海ばあちゃんは、奈保のひいおばあちゃんだ。海のすぐ傍に住んでいたので、みんなから海ばあちゃんと呼ばれていた。
海ばあちゃんの百歳のお祝いに、親戚が大勢集まった時のことだ。海ばあちゃんには八人の子どもと、十九人の孫、三十二人のひ孫がいて、全員が来ていたわけではないけれど、それでも海ばあちゃんの家は人が溢れていっぱいだった。溢れた何人かは目の前の海へ降り、砂浜に敷き物を広げてピクニックをしていた。奈保は十歳で、その中で一番歳が下だったから、首にスカーフを巻いた海ばあちゃんの隣に並べられて、「九十歳違いやねえ」と親戚たちに代わる代わる写真を撮られた。
奈保は海ばあちゃんが大好きだった。母に連れられて会いに行く度、海ばあちゃんは電動ベッドの傍へ近付くよう手招きし、のんびりした声で「奈保ちゃんは、由利子ちゃんの娘で、由利子ちゃんは、篤子の娘。篤子はわたしの娘やね。みんなかわいい、みんないい子」と、噛みしめるように口にした。ベッドの枕元には単語帳みたいに穴をあけてリングを通した写真が束になって置かれ、子と孫とひ孫が写るその裏面に、マジックで名前と生まれ年が書かれていた。
海ばあちゃんは、「今日撮った写真も入れとくわ」と奈保の頭を撫でた。それからふと思いついたように、「そうじゃ、ええもんあるんやったわ」と声を上げた。和室の棚に手を伸ばして取り上げた箱を手に、「ええもんきたよ」ともったいぶってみせた。奈保が「なんかな」とドキドキしながら覗き込むと、蓋をそっと開け、中を見せた。ハタダの栗タルトだった。
「なーんじゃ、栗タルトか」
奈保の声ががっかりしていたからだろう、海ばあちゃんは「好きじゃなかったか?」と首をかしげた。奈保はうーんと唸って、
「ええもんって言うけん、ケーキやと思った。生クリームの」
と口を尖らせた。海ばあちゃんは、そうかあ、ごめんなあ、ケーキはないわあ、と箱を閉じ、ポケットから折り畳んだ千円札を取り出すと奈保の手に握らせ、「帰りにお母さんに買ってもらい」と、もう一度奈保の頭を撫でた。
奈保は「ありがとう」とお礼を口にしながら、海ばあちゃんの顔が見られず俯いた。内心(やってしまった……)と泣きそうだった。栗タルトも好きなのに。誕生日のお祝いだからケーキがあるかもしれないと期待してしまったのだ。海ばあちゃんのお祝いなのに、きっと、悲しませてしまった。
黙ってしまった奈保に代わって、隣にいた母が「海ばあちゃん、わたし栗タルト食べたいわ」と話を引き継ぐと、「ほうかね。いっぱい食べえ」と海ばあちゃんが嬉しそうに声を弾ませ、箱を差し出した。
別の機会に、今度は祖母の家で栗タルトが出された時に、
「この間、海ばあちゃんが栗タルトくれようとしたのに、いらんって言ってしもた」
ともらすと、祖母は「ええんよ」と奈保を許した。
「海ばあちゃんは、奈保ちゃんの顔見れただけで、とびきりうれしいんじゃけん、気にせんでええんよ」
けれど奈保は気にした。気にすることは自分にしかできなかった。栗タルトを頬張り、ほんのりと柚子が香る餡の甘さを口の中に感じながら、あの時も「ほしい」って言えばよかった、と繰り返し後悔した。そんな奈保を知ってか知らずか、祖母が「そういえば」と話し始めた。
*
百歳のお祝いに、親戚がいっぱい来とったでしょう。わたしは海ばあちゃんの八番目の子どもでね、上に七人きょうだいがおるんよ。ひいおじいちゃんはわたしが生まれてしばらくして病気で死んでしもうたけん、海ばあちゃんがたくさん働いて育ててくれた。朝から畑に出て、日が暮れたら洋裁のお仕事をしとった。戦争のすぐ後だったけん、食べるもんもようけあるわけじゃなくてね、甘いもんなんかは、あはは、歳取ってからの方が食べよるね。アイスとかケーキとか、今はいくらでもあるけど、子どもの頃はお菓子なんか全然家になかったんよ。
栗タルトもね、大人になってから初めて食べたね。奈保ちゃんのお母さんを産んだ頃、海ばあちゃんが買ってきてくれたんよ。「こんなおいしいもんあるんよ、知っとった?」って。後で知ったけど、その頃発売されたばっかりやったんやって。
その頃には海ばあちゃんの子どもはみんな独立して、孫も生まれて、海ばあちゃんも生活に余裕があったけど、好きな食べ物を好きなだけ買ういうんがもう、昔っからの習慣でできんのよね。なるべく安いものをちょっとだけ買うのに慣れとるから。ほんでも、栗タルトだけは時々の贅沢として買いよったんよ。みんなに分けながら、
「一本まるまる食べてみたいねえ」
なんて言うけん、「食べたらええやん!」って言いよったんじゃけどね。「もう十分やわ。大丈夫やわ。お腹いっぱい」言うて、みんなに食べさせるん。
子どもや孫やひ孫が嬉しそうなん見るのが楽しいんやろうっていうのも分かるんじゃけどね、栗タルトを一本まるまる食べるくらいの夢、叶えたらええやん、ってちょっと悲しくも思ってたん。
*
海ばあちゃんは、百一歳の誕生日を迎える前に亡くなった。
奈保は煌々と明るい東京のスーパーで、突然現れた栗タルトをいくつかの総菜と一緒にレジに通し、マンションまで歩いて帰る道すがら、母に電話をかけた。
「遅くまでお疲れさま」と労う母に、「近所のスーパーに栗タルト売りよってびっくりした。思わず買うてしもたわ。まるまる一本も。一人暮らしなのに」と話すと、母は「毎日ちょっとずつ食べたらええやん」と笑い、それから、「まるまる一本いうたら、海ばあちゃんが、一人で一本全部食べたって話しよったことがあったなあ」と言った。奈保は思わず立ち止まり、「ほんまに?」と聞き返す。
「うん。奈保がまだ小さい頃よ。っていうても、海ばあちゃんはだいぶ歳取っとったけん、一人でまるまる一本も、よう食べられたねえってびっくりしちゃった」
そうなんや……、とどこかほっとした気持ちでつぶやき、再び歩き始める。
「海ばあちゃんね、とうとう食べてしもたあ! って、はしゃいどった」
耳元で母が嬉しそうに言った。
奈保はテーブルの上に栗タルトを置いた。東京の部屋に栗タルトがあるのは、不思議な気分だった。箱から取り出して包装を解くと、一番端の一切れから、指でつまんで食べた。昔から変わらない餡の優しい味がする。一切れ、もう一切れ……後もう一切れだけ。残りはまた明日。明日は、もうミスしないように、慎重に仕事をしよう。明後日も、そのまた次の日も。「気にしなくて大丈夫。失敗して覚えていくものなんだから」という先輩の言葉を思い出す。気にはする。気にはするけど、失敗して、覚えて、進んでいくしかないのだ。
一本まるまるの栗タルトを前に、(これ全部、一人で食べちゃうんだな)と思うと自然と口元がほころんだ。海ばあちゃん、と心の中で呼びかける。ほんまじゃ、特別においしいね。